動物介在教育とは
「動物介在教育」という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、どのような意味を持ち、実際にどのような教育が行われているかまで、ご存じの方は少ないのではないでしょうか。
動物との共生は、決して動物を「守る」「かわいがる」ということではなく、違う種である彼らを尊重し、彼らの能力や特性を活かし、共に生きること。
共に生きる方法の1つとして考えられる「動物介在教育」。今回は、数年にわたりその活動をされており、ホリスティックケア・カウンセラー養成講座の1,2章を担当していただいている須﨑 大先生に、「動物介在教育の現場から」お話いただきます。
…………………………………………………
前回は、動物介在教育の現場で起きている奇跡についてお話ししました。今回はこれからの動物介在教育の課題と展望について、お話したいと思います。
私たちは東京学芸大学との共同研究を通し、動物を介在させることによる児童の学習の可能性について、各学年・科目において検証してきました。今後もさまざまな科目において、道徳教育を加味したカリキュラムの構築が期待されます。検証結果については、介在犬とのふれあいに留まらず、動物を介在させることによる道徳的価値についての理解を基に、児童が自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考えられるよう、学習プログラム開発に反映させていく必要があります。
【家庭犬の可能性】
私たちの活動に参加する介在犬は、介在教育を生業とするワーキングドッグではなく、一般の家庭犬です。ワーキングドッグは専門分野によって用途は多岐にわたり、それぞれの個性を活かした活動をしています。
動物介在教育は安全第一で進められるため、噛むといった行動は許容されません。しかし被毛を引っ張られるなど、嫌なことをされたときに「嫌だ」という表情やボディランゲージで表現することは、「感情をもつ犬」にとって当然であり、私は問題ないと考えています。「犬にも嫌なことがある」ということを、その都度、ハンドラーが児童に伝えることで「犬にも感情や気持ちがある」ことを学ぶ大事な機会になると考えています。
【汎用性を持たせるための課題】
私たちが直面している主な課題は次の通りです。
・介在犬とハンドラーの育成
・介在犬の条件の設定
例)
-子どもの声に過度に反応しない(場所、タイミングに因らない)
-身体のウィークポイントのリリース
-咬傷経験の有無 など
・介在犬ハンドラーの条件設定
・介在犬との良好な関係性
・犬に対する経験値
・知識
・教育的指導の学び(児童への接し方、話の組み立てなど)
現場でのハンドラーは、児童に直接的なアプローチをする立場でもあるため、教育的指導が求められます。そのため介在犬だけでなくハンドラーにも、的確なガイドラインを作成していく必要があります。
【カリキュラム実施の最大の懸念点】
<子どものアレルギーについて>
保護者の心配のひとつに、子どものアレルギーについての懸念があります。アレルギー児童の割合については、下記既存データがあります。
私たちが開催している『命の授業』で、児童に対して保護者に事前アンケートを行った結果、「児童にアレルギーがある」答えたのは、1クラスあたり1.7名でした。保護者が条件付きで参加可能と判断した割合が約98%。保護者が参加不可能と判断した割合は約2%。授業後、実際に犬と接触をもてなかったのは、全体の約0.1%のみでした。つまりアレルギー自体の懸念があるものの、45分という短い時間内、児童が自ら介在犬に近づき、触ることができたのです。
事前アンケートで「犬が怖い」と答えたのは全体の8%、1クラス約2.6名で、当日の授業では1クラス約5名、全体の17%でした。6,700名中、1,139名の児童が実際に犬を目の前にして「怖い」と感じて触ることをためらいました。しかしながら、授業が終わるまで恐怖心が取り除けなかった児童は全体の中で2名のみで、動物を通じた学びが児童の心に大きな変化を与えていると言ってよいと思います。
アレルギー対策については、授業前の犬たちの健康管理やシャンプーの義務に加え、現場でのケアが重要だと考えています。アレルギーの度合いを鑑みて、介在犬との距離を調整したり、関係者が把握しやすいように帽子の着用を行ったりして配慮しています。
ただ、事前アンケートで「アレルギー」や「恐怖心」を提示されるご家庭ほど、犬に触りたがるという事実もあり、実際のところ現場で、児童の行動や反応を見ながら対応しているというのが現実です。
【これからの展望】
今日まで、全国96校約6,700人の児童を対象に行なってきた中で感じることは、介在犬が登場するまでは奇声を上げていたような児童が、犬を目の前にすると案外やさしい声かけや動きをしたり、授業前は「犬が怖い」といっていた児童が、自ら犬に触れることは多々あり、感受性の高さが活かされる分野でもあるという点です。
先日、若年層の一番の死因は自殺だという記事がありました。犬は自殺しません。その犬から児童がもらうもの、そして児童が犬に与えられるものがあるとすれば、「犬はかわいい、癒しになる」を超えた学びが存在するのではないかと、これからの動物介在教育、及び道徳教育の可能性を期待してなりません。
【家庭犬にとっての学び】
慣れない環境(小学校など)で歓喜に湧く児童の前で自制に努め、ときには触手などを許容するのは容易なことではありません。しかしながら、それこそ日常生活で起こりうるシチュエーション例のひとつともいえます。カフェで子どもが騒いでいても、ついつられて吠えずに穏やかに過ごす。子どもが近づいてくることがあっても、怖がることなくあいさつができるなど、実際に動物介在教育に介在する犬とその飼い主(ハンドラー)は、活動に携わることで、必然的に日常生活での課題の克服にも成功することにつながり、犬はもちろん、ご家族のQOL(クオリティ・オブ・ライフ/生活の質、人生の質)の向上も期待できるのです。
昨今捨てられる犬の多くは「吠え」や「噛み」が理由によるものです。そして飼い主の一方的な都合により飼育放棄されているのが現状です。この活動に携わる犬たちは子どもたちにとっての「先生」でもあり、そんな誇り高い犬は多くの人に愛され、必ずや生涯飼育を獲得するでしょう。
「犬を飼うのがこんなに大変だとは思わなかった」「この犬は私には合わない」といった信じがたい放棄理由を目の当たりにすると、子どもの頃に、動物に対する適切な情報や経験の機会をもっと作る必要性があるのではないかと感じるのです。
【教育のプロと動物の専門家が手を取り合うことの可能性】
主役は子どもたちです。普段私たち専門家は、大人を相手に説明をすることが多いですが、授業では真っ白なハートをもった児童に、わかりやすく、効率的に伝えていく必要があります。さらには感覚で伝えるのではなくロジカルに。そしてただ単に「楽しかった」というふれあい活動で終わらせるのではなく、体験したことが自身の実生活とどのような関連性があったのか? という自分事としての「学び」の機会を与えること。教育のプロと動物の専門家が手を取り合うことによって、「動物とのふれあい」を超えた学習プログラムの開発が期待できると考えています。
【家庭犬の社会的認知度を上げる】
現在、飼育放棄された犬を再度譲渡するための「保護団体」も増えて、譲渡数自体は増長傾向ですが、未だ多くの犬が日々飼育放棄されています。本活動を通して、介在動物として活動する家庭犬の存在意義と社会的認知度を上げることも付加的価値になり得ると、動物業界全体としても期待しています。動物介在教育(A.A.E.)は未だ発展途上であり、専門家や専門機関と積極的に連携し、子どもの心を育てるような、生命尊重を目指す活動の充実が望まれます。
動物とのふれあい活動が体験に留まらず、道徳科、生活科や総合的な学習の時間など、教育の現場に取り入れられるよう、今後は教師を中心に「教育」というロジックを基軸とした「動物介在学習プログラム」を開発し、永続的な調査研究が必要です。
昨今はホリスティックケア・カウンセラーをはじめ、数多くの犬に関わる専門家が存在しています。その多くが潜在的で、実質的な活動を行っていない方々も多くいますので、そういったみなさんに活動の場を提案できる機会にもしたいと思っています。また教育者OBの方々の中で、犬に真意的な方に向けて、セカンド・ライフ的な提案もできたらステキだなと思っています。
【最後に……】
先進国・日本であっても、今7人に1人の子どもが1日に3食、食べることができないそうです。少なくとも私が子どもの頃は、子ども同士や大人との交流の機会はありました。しかし今はそれすらも制限され、例えば卒業写真に載せる思い出の写真もないそうです。修学旅行も、運動会や文化祭も制限されている現代、私たち大人にできることは何でしょう。こういう社会情勢だからこそ、それぞれが自分のフィールドでできることを想像し、手をつなぎ、想いを具現化していく、そういう気持ちと行動が求められていると思います。
引き続き、社会的立場が弱い子どもや動物たちの負担を軽減し、笑顔溢れる社会に少しでも近づけるよう願いつつ、私たちの活動の質を高めていきたいと強く思い、これからも活動を進めていきます。
引用:ホリスティックケア・カウンセラー・コラム







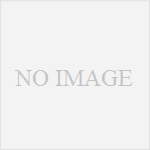
コメント